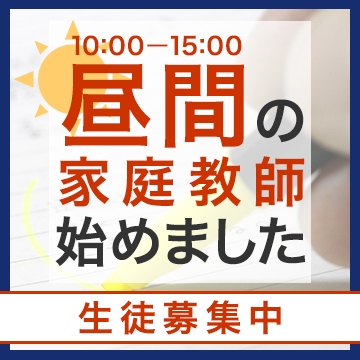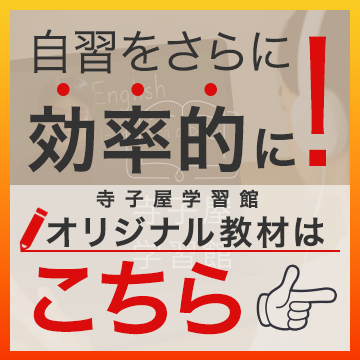文系か理系か? 迷ったときは…
たいていの高校は、2年生に上がるときに文系と理系に別れます。僕は高校時代、文系でした。国語が大の苦手の文系。そして数学がまあまあ得意な文系の生徒でした。
高校1年生のとき、担任がことあるごとに「文系か理系か?進路で悩んだときは理系にしとけ。あとになってから文転はできるけど、
文系の生徒が理系に変更することは無理だぞ。」
と言っていました。
要するに、理系の場合、あとになってから文系に変更することはできるが、文系の生徒が後になってから理系に変更することはかなり難しい、ということです。
文系か理系か? ほとんどの生徒さんにとって決め手は「数学ができるかどうか?」だと思います。
国公立大学を目指す場合、文系の受験生でも共通テストで一般的には数学を受験しなければなりません。
2次試験には数学は必要ない大学が多いですが、共通テストで数学が必要になってきます。
そのため、文系の受験生でも数学を勉強しなければなりません。
これが私立文系になると、試験科目はほとんどの場合「英語・国語・社会」の3教科になります。
数学が必要ない分、英語・国語(現代文と古文)・社会のみを勉強すればいいことになります。
どんなに遅くても,高3の夏休みに入るまでには自分は文系なのか?理系なのか?を決断する必要があります。
理系の受験生の場合は、極端な話共通テストが終わってからでも文系に変更、または理系と文系の両方の大学(学部)を受験することも可能です。
文系の大学で2次試験に数学が必要な国公立大学を受験すれば、かなり有利でしょう。
それだけ理系は融通が効きます。
実際、僕がいた新潟大学教育学部小学校数学科の学生の5割は「高校時代は理系の人」でした。
新潟大学の教育学部小学校数学科は、2次試験に数学が必要で、配点も2次試験だけで300点もありました。
「やや理系向けの文系」の学科でした。
実際、大学に入ると専門教科は数学で、2年生のときは毎日のように数学を勉強しました。
たとえば富山大学の理学部を受験した受験生が、新潟大学教育学部も受験した、など理系の大学と新潟大学を受験する、という組み合わせの学生もいました。
理系の受験生が文系の大学(2次試験に数学がある大学)を受験すると、」かなり有利になります。
しかも文系の場合は、ほとんどの国公立大学で2次試験の数学には「数Ⅲ(微分積分)」は試験科目には含まれていません。
理系の受験生にとっては文系数学の2次試験といっても、数学は他の受験生と差をつける「チャンス科目」になります。
または共通テストでこけてしまった場合、急きょ文系の大学に志望校を変更することも可能です。
いずれにせよ「迷ったら理系」という選択は、おススメだと思います。
2025年02月21日 05:10