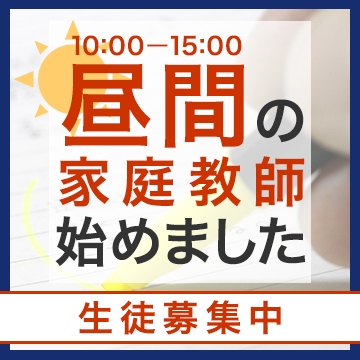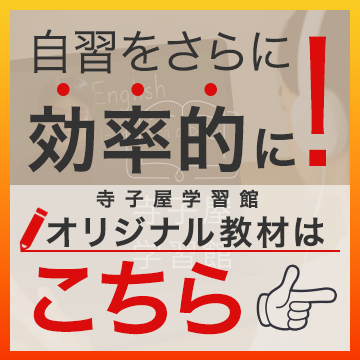忘却曲線
僕が高校1年生のとき、化学の先生が、ことあるごとに「学校で習ったことを家に帰ってから8時間以内に必ず復習すること」とおっしゃっていました。その先生は富山中部高校に長年勤務されていた、実績のあるベテラン先生でした。
当時の僕は「何でことあるごとに8時間以内?なのだろう」と不思議に思っていました。
やがて大学に進学し、教員採用試験の勉強をしているときに「忘却曲線」のことを知りました。
忘却曲線とは、「記憶の保持時間の経過に伴って、忘却が進行する様子を数量的に表したもの。」
ドイツの心理学者,ヘルマン・エビングハウスが発表したものです。
わかりやすく説明すると、習ったことを早いうちに復習すると、学習内容が定着しやすい。
逆に習ったことを放置していればしているほど、学習内容を忘れていってしまう、というものです。
時間が経過すれば経過するほど、人間は忘れていきますよね?
そうならないために、早いうちに繰り返し復習していくと、定着率がグンと上がる、ということです。
僕自身の経験を振り返ってみると、高校時代の英作文の勉強にこの説がぴたりと当てはまっていました。
高校2年生の4月に学校から桐原の「即戦ゼミ3」という、受験生の間では定番となっている文法・英作文の問題集をもらいました。
僕はこの即戦ゼミの勉強をするときに、ただ問題を解いて( )内に単語を入れていく、という勉強の仕方はせず、( )に単語を入れた状態でできた
英作文を1つずつ単語カードにして、英文ごと丸暗記していきました。
そのときに、忘却曲線の話になりますが、その日に覚えた英文30個くらいを3日後に復習して、そのときに完璧に書けなかった英文カードだけを取り出し、
そのカードを集めて1つのまとまりにして、そのまとまりの英文カードを1週間後に復習する、という勉強の仕方を繰り返していました。
2年生の1学期のみ、このような勉強を繰り返していました。
もちろん、単語を覚えるよりは楽しく、英単語を覚えるよりも英文の方が覚えやすく、知らない単語を覚える必要もないので、
1学期の間に英文カード600枚くらいを覚えてしまいました。
それ以降、進研模試を受けるたびに、この時に覚えた文法・英文を元に答えられる問題がとても多く、卒業するまで英作文の勉強はいっさいしませんでした。
その代わりにこららの英短文カードを,ことあるごとに復習していました。
よく「英単語は文章の中で覚えた方が定着しやすい」と受験本には書いてありますが、
その性質をうまく活用しているのが「DUO」や「速読英単語」などの参考書(問題集)だと思います。
僕が高校生だったころは「DUO]も「速読英単語」シリーズもまだ存在していませんでした。
今の高校生に英語の勉強法を聞かれたら「即戦ゼミ3」か「DUO」または「速読英単語」をやってみてください、とアドバイスすると思います。
個人的には「即戦ゼミ3」の英文を覚えていくのがおススメかなとは思います。(ただいすべてのページを覚えるのではなく、第1章を中心に覚えていってみたらどうかな?と
思います)
中学生がもしも英作文の勉強をする、と仮定すると、僕の場合は僕が作った「寺子屋文法プリント」の各単元ごとの最後の問題(英作文問題)に出てくる英文をカードにして
ガンガン覚えていくことをおススメします。それ以外の方法は今のところわかりません。
富山県の県立高校入試の英語の問題は後半戦が英作文の問題のオンパレードなので、かなりの量の英作文のストックがないと、ちょっと太刀打ちできません。
受験英語の勉強の仕方として、英単語→文法→長文読解問題→英作文の順で対策を立てていく中学生が多いかと思います。
しかしそんなのんきな勉強の仕方をしていると、気づいたころには本番を迎えています。
志望校にもよりますが、ある程度の進学校を目指されるのであれば、遅くても2年生の夏休みあたりから英短文カードを作っていって、1枚ずつ完璧に覚えていく必要が
あるのかなと個人的には思います。
大学入試とは異なり、高校入試レベルの英作文であれば、マニアックな文章を覚える必要は皆無です。
基本的な英文を確実に1つずつ覚えていく、この作業をひたすら地道に繰り返していけば、かなりの学力がつくと思います(長文の力はつきませんが・・・)
長文の勉強の仕方については、ここでは述べませんが、まずは苦手と思っている英作文の勉強にとりかかってみると良いかもしれませんね?
早めに英作文の勉強をするべきか?後回しにするべきか? どちらでも自分の好きな方を選べばいいと思います。
2025年03月28日 11:54