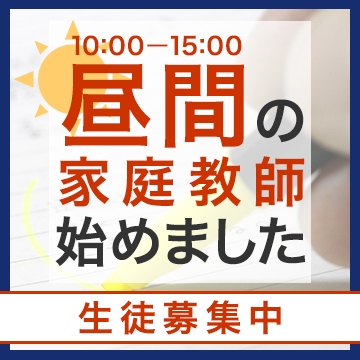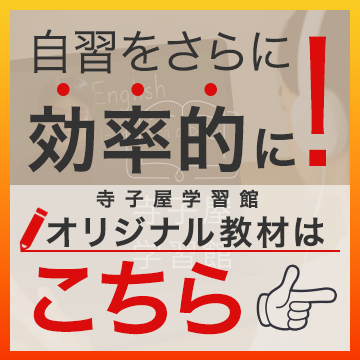1年3か月ぶりの再会 / チャート式数学
今日から8月17日まで、寺子屋学習館はお盆休みになります。そのため、今日の午前中、中学時代の友達(愛知県岡崎市在住)と去年のゴールデンウイーク以来、1年3か月ぶりに会いました。
AM9時に迎えに行って「サウナタロとやま」へ行ったあと、ココス飯野店へ。
娘さんが今年の春から高校生になり、学校のことや勉強・部活のことなど、たくさん話を聞かせてもらいました。
あとはお互いのことなど、気さくに2時間半ほど話しました。
娘さんが合唱部に入っていて、愛知県代表になれたら、今年は富山県(オーバードホール」で全国大会があるため、その時にまた会おう!と言って別れました。
午後からは少し昼寝をして、先ほど文苑堂へ行き、中学生用の歴史の薄い問題集を買ってきました。
今から少し解いてみる予定です。
歴史を苦手としている塾生が多く、「どうやったら歴史が得意になるのかなぁ」と最近、いろいろ考えていました。
ふと、自分の中学時代を思い出していました。
僕も中学1年生のときは歴史が大の苦手で11月に行われた中教研テストでは社会の点数が31点、とういう不名誉な点数をとったことがあります。
2年生になって担任の先生に「先生、どうやったら歴史で点数取れるようになるかね?」と質問したら、先生は
「分厚い問題集じゃなくて、薄い問題集を何冊か解いてみられ」と言いました。
そのことを思い出し、先ほど薄い問題集を買ってきました。
確かにこの問題集だったら、1週間もあれば終わるなぁと思い、歴史の全体像をつかむには良いかな、と思い買いました。
今塾で使っている教材も確かに良いのですが、ただ、内容がかなりあって、歴史嫌いの生徒さんにはちょっと荷が重すぎるかなと感じていました。
例えば、数学の苦手な文系・国公立大学志望の高校生が、絶対にやってはいけない勉強方法は「チャート(黄色)」に手を出してしまい、内容量の多さに圧倒され、
結局全部終わらないまま本番(共通テスト)を迎える、ということです。
確かにチャートは黄色・青色・赤色問わず、大変人気があり、使っている学校も多いと聞きます。
僕自身も高校時代は青チャートを使っていました。
数学の進研模試の全国偏差値が55以上の高校生には確かにチャートは有効かと思います(全部やりきれればの話ですが…)
無敵でしょう。
でも数学オンチな高校生がチャートに手を出しても挫折する可能性が大です。偏差値55以下の生徒さんにはチャートは量が多すぎます。
ではどうするか?
答えは「数学基礎問題精講」から初めて「とりあえず全体像を把握する」ことです。
受験生の間では、ほぼ常識かと思いますが、基礎問はチャートの3分の2くらいしか問題数がなく、確かにチャートほど全体を網羅はしていません。
でも短期間で数学の全体像を押さえるには適しているかと思います。
よほどの完璧主義でもない限り、チャートに手を出す前に「基礎問題精講」をしっかりやってほしいと思います。
武田塾さんの動画でも繰り返し言っておられますが、文系数学苦手な生徒さんには基礎問がベストかなと思います。
あとは共通テスト、センター試験の数学の過去問を解きまくる。青本(駿台予備校),黒本(河合塾)さんの出しているマーク式の共通テスト用の問題集を
ガンガン解きまくれば、それなりの結果はついてくるかと思います。
話はそれてしまいました、すみません。
中学生の歴史の勉強方法にしても、前出の僕の中学時代の担任の先生のおっしゃる通り、まずは薄い問題集(「例えば、歴史15時間完成~」というタイトルの
問題集で全体像をつかんでから、新研究を解いたり入試問題を解きまくれば、少しずつ学習効果が出てくるかなと思います。
中学1・2年生の場合は寺子屋で使っている塾教材がベストだと思いますが、歴史アレルギーな3年生(受験生)には残された時間が少ないので、
本屋さんで売っている薄い問題集(歴史に限らず、地理とか公民とかもおススメです。また、理科に関しても薄い問題集はおススメです)を
購入されて、短時間でとりあえず仕上げる、これが最良の歴史の勉強方法ではないかと思います。
あともう1点注意してほしいのは「年表を全く覚えていない生徒さん」の場合は、語呂合わせで覚える事のできるカラーの参考書を買って、出来事と年代をセットで
覚えるのもとても大切かと思います。
年表をトイレに貼ってトイレで覚えるのも有効ですよ。
僕は実際、中3になってから語呂合わせの覚え方でたくさんの出来事を年表とセットで覚えていったところ、歴史の出来事がスパッと頭に入るようになり、
一気に歴史が得意になりました。
中学1・2年生のときの歴史の先生は、残念ながら僕には授業内容が全く頭に入っていかなく、こんな言い方は失礼ですが、わかりづらい授業でした。
2年生になり、地理の先生がベテランの先生になってからは、一気に地理の成績が上がりました。
中学・高校時代の勉強は、担当の先生の指導力が成績にモロに響くので、ある意味、運もあるかと思います。
人のせいにしてはいけない、と言いますが果たしてそうでしょうか?
僕は大学時代、文系で数学科だったのですが、数学の授業がさっぱりわからず、落ちこぼれになってしまいました。
大学の先生の話している内容が全く頭に入ってこなくて、友達に聞いた方がよっぽどわかりやすく、「高校時代の数学の先生が大当たりで良かった」
と何回も思いました。
僕の場合は中学・高校6年間を通して、数学と英語の先生がとてもわかりやすい先生で、そのおかげで文系数学・英語はまずまずの成績でした。
大学に合格できたのも、先生方の授業のおかげだったと今でも思っています。
さて、夏休みもお盆を過ぎると、あっという間に時間が流れていきます。
受験生はもとより、1・2年生の生徒さんも夏休みの宿題を期限までに頑張って終えてください。
3年生にとっては最後の夏休みですね?
後悔のない、充実した夏休にされてください。応援しております。
2025年08月14日 15:24