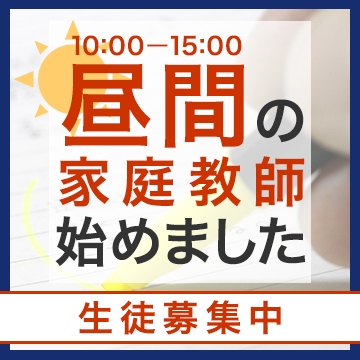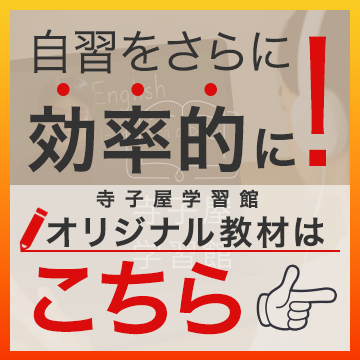小学校時代のサッカー部→中学校時代のサッカー部
僕は小学校2年生の6月1日から小学校を卒業するまで、サッカー部に所属していました。友達がサッカー部に入っていたので「俺もサッカーやってみようかな」と思い、サッカー部に入りました。僕のいたサッカー部は毎年強くて、ただ全国大会には一度も行ったことがないチームでした。
小学校3年生のときから練習が一気に厳しくなり、平日は学校が終わってから夜7時くらいまで(暗くなるまで)、土日は試合というスケジュールでした。
夏休みが地獄で、朝8時~正午まで、そして夕方4時から7時まで、最後にグランド20周という練習メニューでした。今振り返るとめちゃくちゃな練習時間ですね。毎日7時間練習していました。それだけ練習すれば強くもなると思います。僕は全然楽しくありませんでした。ただ試合に勝つことはうれしかったので、やめることなく続いたのだと思います。
悲劇だったのは、小学校5年生のときに、グラウンドにナイター設備が整ってしまったことです。そのおかげで平日は放課後~夜8時まで練習することになってしまいました。監督も5年生からめちゃくちゃ怖い監督に変わってしまったので、ますますサッカー部が嫌になりました。
監督は体罰当たり前の監督だったので、(今だったら大問題ですね)とにかく怖く、少しでもサボってると「ちょっとこっち来い」と言われ、顔をたたかれ、腹を蹴られるという大惨事に… もちろんみんな監督が怖くて一所懸命に練習していました。
僕は4年生までは中盤の選手だったのですが、5年生からはキーパーになりました。当時ドッチボールが得意だったため、僕自ら志願してキーパーになりました。
ところが、いざキーパーになると責任重大で、点を取られるたびに「監督にたたかれるかな」と不安になっていました。
当時、育成リーグというのがあり、僕の小学校はじめ富山市の小学校12チームくらいで前期と後期に分けてリーグ戦を戦っていました。
僕の小学校は6年生のときに2つの引き分けをはさんであとは全勝で、優勝しました。一応うれしかったです。
中学に入り、嫌ながらも僕は友達につられてサッカー部に入りました。ところが…中学のサッカー部はすごく楽しかったです。まず、監督が顧問の先生(学校の先生)だったため、すごく優しい先生で、先輩も優しく、土曜は午後から4時くらいまで、日曜は試合と休みが半々くらい。「小学校と比べると楽やなぁ。楽しいし」と思っていました。
僕はこの中学時代のサッカー部の顧問の先生の影響で「俺も将来は中学校の英語の先生になりたいなぁ」とおぼろげに思い始めました。
今でもその先生のおかげで僕は子ども相手の仕事をさせてもらっています。「とにかく優しく!絶対に上から目線で子どもたちには接しない。極力怒らず」をいつも心がけています。
中学時代のサッカー部の先生に出会えたことは、僕の人生に大きな影響を与えてくれています。
去年の新聞で、そのサッカー部の顧問の先生(当時は30代前半でした)がシニアの試合に出ていて(教員チームでした)得点を入れている記事が出ていて驚きました。
「先生頑張っとるなぁ」と思いました。白髪になっていましたが、変わらずサッカーが好きなのだなあと、うれしく思いました。
2022年06月26日 11:46