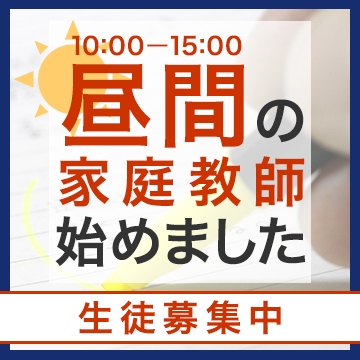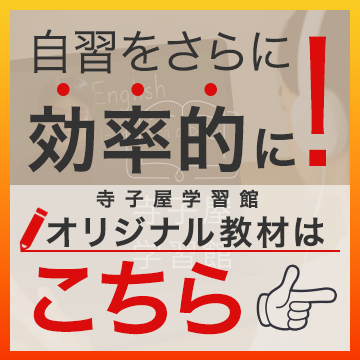中学1年生のときに、僕は仲の良い友達4人でテスト期間になるたびに、お互いのテストの点数を書き、一覧表にして点数を競っていました。
僕の中学1年生の時の成績は学年で288人中120番くらいでした。「平均よりもちょっとだけ上」というレベルでした。
競っていた友達の成績もだいたい110番~180番くらい。「似た者同士のどんぐりの背比べ」の争いをしていました。
当時はそれで満足していました。
ところが、1年生の2月に行われた実力テストで、なぜか僕はいきなり「学年で40番」という好成績を出しました。
理由は今振り返ってもわかりません。まぐれだったのかなと思っています。
ただ1年生の3学期から通っていた塾を替えました。
1年生の12月まで通っていた塾は,授業中はまあまあ楽しく、和気あいあいとしていたのですが、成績には全く響きませんでした。
1年の3学期からは、チラシに書いてあったややスパルタ式の塾に入ることになりました。
その塾に入るには1つ条件がありました。それは「通知票の英語・数学・国語の3教科の合計が
11以上の生徒さんのみ受け付けます」
というものでした。当時の僕の成績は英語5,数学5,国語3 で合計13だったため、何とかその塾に入ることができました。
先生は僕と同じ小学校を卒業されている、30代前半の男の先生でした。個人塾でした。
この塾は僕にとって「当たりの塾」でした。教え方がとても上手で、毎回先生がオリジナルプリントを作ってくれて、その問題を解いていく、
といったスタイルの塾でした。
2年生になりクラス替えが行われ、今度は
違う友達と成績を競うようになりました。
そのときは僕を含めて5人でテストになるたびに成績を一覧表にして競っていました(半分楽しみながら競っていました)
塾が変わったこと、クラス替えがあってライバルの学力が大きく変わったこと が原因なのか、僕の成績は一気に60番も上がるようになりました。
1学期の中間テストで今までの120番→60番に上がりました。もちろんびっくりしました。両親も驚いていました。
当時は「富山南高校に行きたい」と僕は思ていました。僕の学年順位から考えると、ぎりぎり富山南高校ボーダーライン、という成績でした。
2年生になり、一番効果があったのは、
競うライバルの質が変わったことだと思います。
当時、点数を競い合っていた友達はみんな成績が学年で40番~60番くらいでした。
そこに学年順位120番の僕が加わったことになります。
当然、彼らがふだん話している勉強の話にも、最初は僕は全くついていけませんでした。
「〇〇高校に入るには学年順位で〇番くらいじゃないと行けない」
「〇〇高校の目標点数は定期テストだと400点くらいないと厳しい」などなど、
それまでの僕が全く知らなかった話のオンパレードでした。
僕はかなり「焦りました」これは本格的に勉強していかないと、このグループの中の会話にはついていけないなぁ と思いました。
新しい塾の授業はとてもわかりやすく、他の塾生も真剣に授業を受けていたため、僕も良い影響を彼らから受けました。
1年生のときは僕の勉強時間は毎日30分程度。テスト期間になると一日1時間半くらいでした。
2年生になると僕の勉強時間は1時間。テスト期間は一日2時間くらいでした。たいして勉強時間は増えませんでしたが、勉強内容がかなり変わりました。
一番変わったのは英語の勉強方法でした。僕が1年生のときの英語の先生は、新採用の女の先生でした。
まだ若く22歳~23歳の先生だったのですが、とても授業がわかりやすく、英語のテストはいつも90点以上でした。
2年生になると英語の担当の先生が変わってしまい、ショックだったのですが、僕は英語の勉強方法を変えました。
それまでは学校のワークを繰り返し解くだけ という単純な勉強方法だったのですが、2年からは「教科書の和訳」→「
すべて英文に直す」という
英作文中心の勉強方法に変えました。多分、先生に言われたか、友達の真似をしたのかだと思うのですが、この勉強方法は僕にはマッチしました。
最初は和訳を見ても、もちろん正確な英文は書けません。半分以上は間違えていました。
でも何回も繰り返して英作文を書いているうちにコツをつかんできて、単語も熟語も一気に覚え、英文の構造も理解できてきました。
今振り返ると「英作文の勉強」は「英単語→熟語→英文和訳→英作文」というスタイルの勉強方法で考えると、「最終段階での勉強方法」だったのですが
僕は気にせずにひたすら毎日のように英作文を書いていました。
その結果、2年生1学期の中間テストは学年で60番になりました。
当時、数学の先生は(3年間同じ先生でした)女性のベテラン先生で、この先生の授業もめちゃくちゃ上手でわかりやすい授業でした。
僕はラッキーでした。英語・数学の授業がわかりやすく、運が良かったのだと思います。
60番になったことで、友達の話にも少しずつついていけるようになり、一番大きかったのは自分に自信が持てるようになりました。
結局、2年生時代の成績は1年間通して50番~60番でした。上がりましたねぇ。
そして3年生。クラス替えがあり、今度はまた違う友達とテスト結果を競うことにしました。
今度はそのグループのメンバー構成は「学年で1けた」「学年で20番以内」「学年で30番以内」「学年で60番くらい」そして「僕」の5人でのグループになりました。
2年生のときよりも「
さらにレベルアップした友達」と成績を競うようになりました。
学年で1ケタの友達にはさすがに勝てないと思い、「せめて学年で30番以内の友達に追いつきたい!」と思い、
そして3年生になると毎日2時間くらいは勉強するようになりました。
そして迎えた3年生1学期の中間テスト。僕の成績は「学年で
28番でした」
そのころになるともう「これは偶然ではなく、俺の実力だろう」と冷静に分析していました。
僕は当時、富山東高校に行きたい、と強く思っていました。
東高校から富山大学へ行きたい、と思うようになっていました。僕が通っていた個人塾の先生が富大OBだったことも影響を受けました。
「
絶対に東に合格して、富山大学に行きたい!」と真剣に考えるようになりました。
当時、僕の通っていた中学校から富山東高校に入るには学年順位が25番~40番くらい」と言われていました。
僕はなんとか富山東高校レベルの成績には入っていました。ただしこれは「あくまでも
中3の学習内容での成績」でした。
1・2年生の成績はそこまで良くなかったので、担任の先生からは「佐伯の場合は1・2年生の成績が足りてないから、これからは「1・2年生の勉強もしられ」
と言われました。
僕の場合「学年が上がるにつれて成績も上がっていったパターン」だったのですが、特に1年生の学習内容がよくできていなかったため「定期テストは20番台
でも実力テストでは
40番くらいにまで下がっていました。
やっぱり1年生のときの「遊んでいたツケ」が大きかったのだと思います。
3年生の12月からはようやくスイッチが入り、毎日5時間勉強しました。日曜日は8時間くらい勉強しました。
でも結局、僕は富山東高校を受験して、「不合格」に終わりました。
今回のブログで、僕が一番声を大にして言いたいのは「
勉強成果を競い合えるよきライバルを見つけてほしい」ということです。
自分よりも「少し成績の良いライバル」を見つけて、その友達にくらいついていく、ことが一番成績アップにつながると僕の経験を通して思います。
目標となる友達(そんなに仲が良くなくても良いと思います)を見つけて、良い意味で競い合う、これに尽きると思います。
僕は中学3年間通してそのことを学びました。
まだ成績を競いあえるような友達がいない生徒さんは、「自分よりも少しでも成績のよい友達」を見つけて、その友達と競いあってください。
刺激を受けて成績は上がっていくことが多いと思います(もちろん勉強をしなかったら、いくら頭の良い友達がいても効果はありませんが)
決して「井の中のかわず」にならず、思いっきり背伸びしてみてください。
もちろん志望校を具体的に決めるのも勉強するきっかけ になると思います。
「
自分で想像できないことは実現しない」と聞いたことがあります。
将来、志望校で勉強している自分、志望校で仲間と楽しく過ごしている自分を想像してみてください!
頑張ってください。応援しています。
2025年09月16日 10:58